コードネームは「ルート音+コードタイプ+拡張音」の3要素で構成されています。例えば「Dm7」なら「D(ルート)+m(マイナー)+7(セブンス)」となり、「レ・ファ・ラ・ド」の4音で構成されます。
この仕組みを理解すれば、初見のコードでも構成音が予測でき、ギターでの押さえ方や代替コードの発見が容易になります。音楽理論の基礎として、すべてのギタリストが習得すべき重要なスキルです。
コードネームの基本構造と読み方
コードネームの3つの構成要素
コードネームは以下の3要素で構成されます。
- ルート音(Root): コードの基準となる音
- コードタイプ(Quality): 長調・短調・減和音などの種類
- 拡張音(Extensions): 7度、9度、11度などの追加音
基本的な記号体系
メジャーコード(長三和音):
- 記号: 何も付けない、またはM、maj
- 例: C、CM、Cmaj
- 構成: ルート+長3度+完全5度
マイナーコード(短三和音):
- 記号: m、min、-
- 例: Dm、Dmin、D-
- 構成: ルート+短3度+完全5度
セブンスコード:
- 記号: 7(ドミナント7th)、M7やmaj7(メジャー7th)
- 例: G7、CM7
- 構成: 三和音+7度音
読み方の実例
複雑なコード例「F#m7♭5」の分解:
F# : ルート音(ファ#)
m : マイナー(短3度)
7 : セブンス(短7度)
♭5 : フラット5(減5度)構成音: F#・A・C・E
コードの構成要素(ルート・3度・5度・7度)
インターバル(音程)の基礎
コード構成を理解するために重要な音程関係
| 音程名 | 半音数 | Cからの例 |
|---|---|---|
| 完全1度 | 0 | C |
| 短2度 | 1 | D♭ |
| 長2度 | 2 | D |
| 短3度 | 3 | E♭ |
| 長3度 | 4 | E |
| 完全4度 | 5 | F |
| 減5度 | 6 | G♭ |
| 完全5度 | 7 | G |
| 増5度 | 8 | G# |
| 短6度 | 8 | A♭ |
| 長6度 | 9 | A |
| 短7度 | 10 | B♭ |
| 長7度 | 11 | B |
| 完全8度 | 12 | C |
基本三和音の構造
メジャートライアド(長三和音):
- 構成: ルート+長3度+完全5度
- C: C・E・G(ド・ミ・ソ)
マイナートライアド(短三和音):
- 構成: ルート+短3度+完全5度
- Cm: C・E♭・G(ド・ミ♭・ソ)
ディミニッシュトライアド(減三和音):
- 構成: ルート+短3度+減5度
- Cdim: C・E♭・G♭
オーギュメントトライアド(増三和音):
- 構成: ルート+長3度+増5度
- Caug: C・E・G#
7度音の追加パターン
ドミナント7th(属七の和音):
- 表記: 7
- 構成音: メジャートライアド+短7度
- G7: G・B・D・F
メジャー7th:
- 表記: M7、maj7、△7
- 構成音: メジャートライアド+長7度
- CM7: C・E・G・B
マイナー7th:
- 表記: m7
- 構成音: マイナートライアド+短7度
- Dm7: D・F・A・C
マイナーメジャー7th:
- 表記: mM7、m△7
- 構成音: マイナートライアド+長7度
- CmM7: C・E♭・G・B
具体例で学ぶコード分析方法
Step1: ルート音の特定
コードネームの最初のアルファベットがルート音です。
例:
- Em7 → E(ミ)がルート
- F#dim → F#(ファ#)がルート
- B♭M7 → B♭(シ♭)がルート
Step2: コードタイプの判別
ルート音の後ろの記号でコードの性質を判断:
判別表:
記号なし/M/maj → メジャーコード
m/min/- → マイナーコード
dim/° → ディミニッシュコード
aug/+ → オーギュメントコード
sus4 → サスペンデッドフォース(サスフォー)
sus2 → サスペンデッドセカンド(サスツー)Step3: 拡張音の追加
基本の三和音に追加される音を確認:
実例分析「Am7♭5」:
A → ルート音(ラ)
m → マイナー(短3度:ド)
7 → セブンス(短7度:ソ)
♭5 → フラット5(減5度:ミ♭)
構成音: A・C・E♭・GStep4: ギター指板での確認
Am7♭5の押さえ方例:
1弦: X(弾かない)
2弦: 1(C:ド)
3弦: 0(G:ソ)
4弦: 1(E♭:ミ♭)
5弦: 0(A:ラ)
6弦: X(弾かない)楽曲での実例分析
「Autumn Leaves」のコード進行分析:
| Cm7 | F7 | B♭M7 | E♭M7 |
| Am7♭5| D7 | Gm | Gm |各コードの構成音:
- Cm7: C・E♭・G・B♭
- F7: F・A・C・E♭
- B♭M7: B♭・D・F・A
- E♭M7: E♭・G・B♭・D
よくある記号と省略表記の落とし穴
落とし穴1: メジャー7thの表記混同
間違いやすい表記:
C7 → ドミナント7th(短7度)
CM7 → メジャー7th(長7度)
Cmaj7 → メジャー7th(長7度)
C△7 → メジャー7th(長7度)覚え方: 「7」だけならドミナント7th、「M」「maj」「△」が付いたらメジャー7th
落とし穴2: sus4とadd9の違い
sus4(サスフォー):
- 3度音を4度音に置き換え
- Csus4: C・F・G(3度音Eが消える)
add9(アドナインス):
- 3度音はそのまま、9度音を追加
- Cadd9: C・E・G・D(3度音Eは残る)
落とし穴3: 分数コード(スラッシュコード)の読み方
表記例: C/E、Am/C、G/B
意味:
- スラッシュの左 → 上の構成音
- スラッシュの右 → ベース音(最低音)
C/Eの構成:
- 上部構造: Cメジャーコード(C・E・G)
- ベース音: E
- 実際の音: E・C・E・G(ベースがE)
落とし穴4: 異名同音の表記
同じ音でも表記が異なる場合があります:
G# = A♭
C# = D♭
F# = G♭楽曲のキーによる使い分け:
- キーE → F#を使用
- キーF → G♭を使用
ケース別Q&A
Q1: 「C6」と「Am/C」は同じ構成音だけど、使い分けは?
A: 構成音は同じ(C・E・G・A)ですが、音楽的機能が異なります:
- C6: Cメジャーコードに6度音を追加した安定したコード
- Am/C: Amコードのベースがクリシェ(経過音)的にCになった形 楽曲の文脈とベースラインの動きで判断します。
Q2: テンションコードの数字(9、11、13)はどう読むの?
A: オクターブを超えた拡張音を表します:
- 9th: 2度音のオクターブ上(C9ならD音)
- 11th: 4度音のオクターブ上(C11ならF音)
- 13th: 6度音のオクターブ上(C13ならA音)
通常、9thには7度音も含まれます(C9 = C・E・G・B♭・D)。
Q3: 「omit」や「no」が付いたコードはどういう意味?
A: 特定の構成音を「省略する」という意味です:
- Comit3: 3度音を省略(C・G)
- C7no3: 3度音なしの7thコード(C・G・B♭)
- Gno3: 3度音なしのGコード(G・D)
パワーコード(5thコード)も実質的にはomit3です。
Q4: 同じコードネームでも押さえ方が複数あるのはなぜ?
A: ギターは同じ音を複数のフレットで演奏できるため、様々なヴォイシング(音の配置)が可能です:
- クローズドヴォイシング: 構成音が密集
- オープンヴォイシング: 構成音が分散
- ドロップヴォイシング: 最高音を1オクターブ下げる
楽曲のキーやメロディーに応じて最適な押さえ方を選択します。
Q5: ジャズコードとポップスコードで表記が違うことがある?
A: ジャンルによって慣例的な表記の違いがあります:
ジャズ系:
- メジャー7th → △7
- マイナー → -(ハイフン)
- ディミニッシュ → °
ポップス系:
- メジャー7th → M7、maj7
- マイナー → m
- ディミニッシュ → dim
ギタリスト向け実践ツールとコード早見表
基本コードタイプ一覧表
| コードタイプ | 記号 | 構成音(Cの例) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| メジャー | C, CM | C・E・G | 明るい響き |
| マイナー | Cm | C・E♭・G | 暗い響き |
| ドミナント7th | C7 | C・E・G・B♭ | 不安定、解決したくなる |
| メジャー7th | CM7 | C・E・G・B | 洗練された響き |
| マイナー7th | Cm7 | C・E♭・G・B♭ | ジャズ的な響き |
| ディミニッシュ | Cdim | C・E♭・G♭ | 緊張感のある響き |
| オーギュメント | Caug | C・E・G# | 浮遊感のある響き |
| サス4 | Csus4 | C・F・G | 浮遊感、解決感を求める |
ギター指板でのコード構成音確認方法
5弦ルートCコードの構成音マップ:
|------|------|------|------|------| ← 1弦
|------|------|--●--|------|------| ← 2弦(E)
|------|------|--●--|------|------| ← 3弦(C)
|------|------|--●--|------|------| ← 4弦(G)
|--●--|------|------|------|------| ← 5弦(C)
|------|------|------|------|------| ← 6弦
3f 4f 5f 6f 7fコード進行での実践チェックリスト
楽曲分析時のコードネーム解読手順:
□ Step1: ルート音を特定(最初のアルファベット)
□ Step2: コードタイプを判別(m、7、dim等)
□ Step3: 拡張音・変化音を確認(♭5、#11等)
□ Step4: 分数コードの場合はベース音を確認
□ Step5: ギター指板上での押さえ方を検索
□ Step6: 楽曲のキーとの関係を分析
頻出コード変化パターン
ドミナントの変化:
G7 → G7alt → G7#11 → G7♭13
マイナー系の変化:
Dm → Dm7 → Dm9 → Dm6
メジャー系の発展:
C → CM7 → C6/9 → Cadd9
まとめ
コードネームは音楽理論の基礎として、すべてのギタリストが習得すべき重要なスキルです。この記事で解説した内容を要点整理すると以下の通りです。
重要ポイントの再確認
1. コードネームの3要素構造
- ルート音: コードの基準音(C、F#、B♭など)
- コードタイプ: 長調・短調・減和音などの性質
- 拡張音: 7度、9度、テンション音などの追加要素
2. 実践的な活用方法
- 楽曲分析でのコード機能理解
- ギター指板での効率的な押さえ方発見
- 他の楽器奏者との円滑なコミュニケーション
3. 学習の進め方
- 基本三和音から段階的に拡張音を学習
- 実際の楽曲で理論を実践確認
- 異なるヴォイシングでの演奏経験を積む
次のステップ
コードネームを理解したら、以下の学習に進むことをおすすめします:
- コード進行理論: 機能和声とコードの繋がり
- スケールとの関係: 各コードで使用可能なスケール
- リハーモナイゼーション: より洗練されたコード選択
- ヴォイシング研究: 同じコードの様々な響き方
実践のコツ
日々の練習で以下を心がけましょう:
- 新しいコードは必ず構成音を確認
- 楽曲のコード進行を理論的に分析
- 同じコードでも異なるポジションで演奏
- 他のギタリストとのセッションで理論を実践
コードネームの仕組みを理解することで、ギター演奏の表現力と理解力が格段に向上します。継続的な学習と実践により、音楽理論を演奏に活かせるギタリストを目指しましょう。
用語集
ルート(Root)
コードの基準となる音。コードネームの最初に記される音
トライアド(Triad)
3つの音で構成される基本的な和音(三和音)
セブンス(7th)
基本の三和音に7度音を加えたコード
テンション(Tension)
9度、11度、13度などの拡張音。コードに色彩感を与える
ヴォイシング(Voicing)
コード構成音の配置や順序。同じコードでも響きが変わる
インヴァージョン(Inversion)
転回形。ルート以外の構成音を最低音にしたコード
オルタード(Altered)
変化音を含むコード。特にドミナント7thコードの変化形
エクステンション(Extension)
7度以上の音程を含む拡張されたコード
サブスティテューション(Substitution)
代理コード。元のコードの代わりに使える別のコード
ドミナントモーション
属和音から主和音への強い解決進行(V→I)
クロマチック
半音階的な音の動き
ディアトニック
特定のキー内の音のみで構成されるコード
モーダル
教会旋法に基づくコード進行やハーモニー
ポリコード
2つ以上のコードを重ねた複合コード
クラスター
隣接する音程で構成される密集和音
参考文献・出典
学術・教育機関
- バークリー音楽大学「現代ハーモニー理論」
- 国立音楽大学「和声学概説」
- 東京音楽大学「ジャズ理論基礎」
専門書籍
- 「ギタリストのためのコード理論」(リットーミュージック)
- 「実践コードワーク」(中央アート出版社)
- 「ジャズ・ハーモニー入門」(音楽之友社)
- 「コード進行スタイル・ブック」(リットーミュージック)
国際的標準
- Real Book(ジャズスタンダード集)
- Berklee Jazz Standards(バークリー版)
- The New Grove Dictionary of Music(音楽事典)
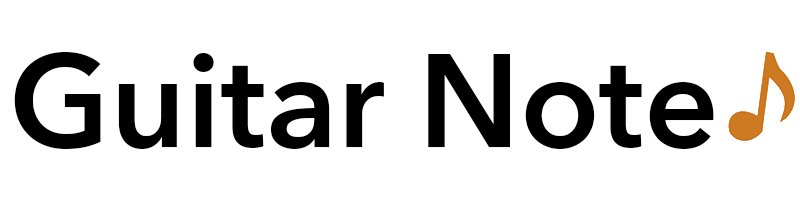
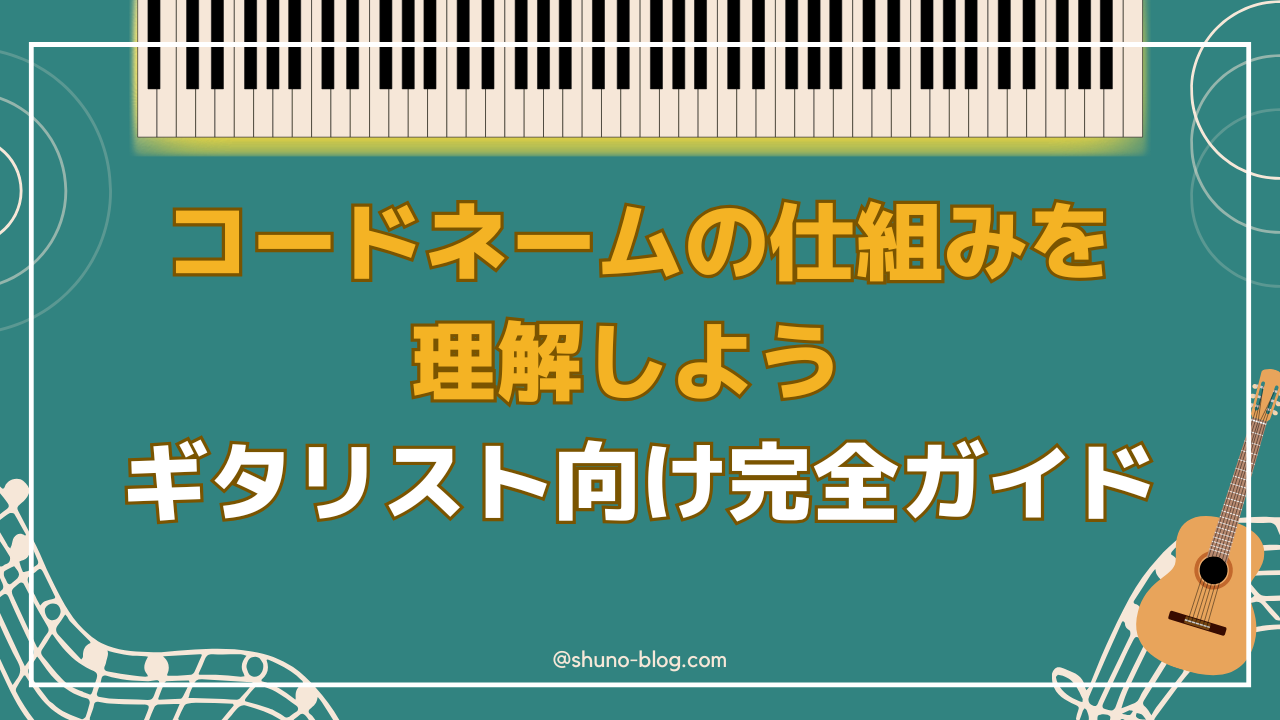

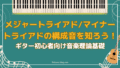
コメント